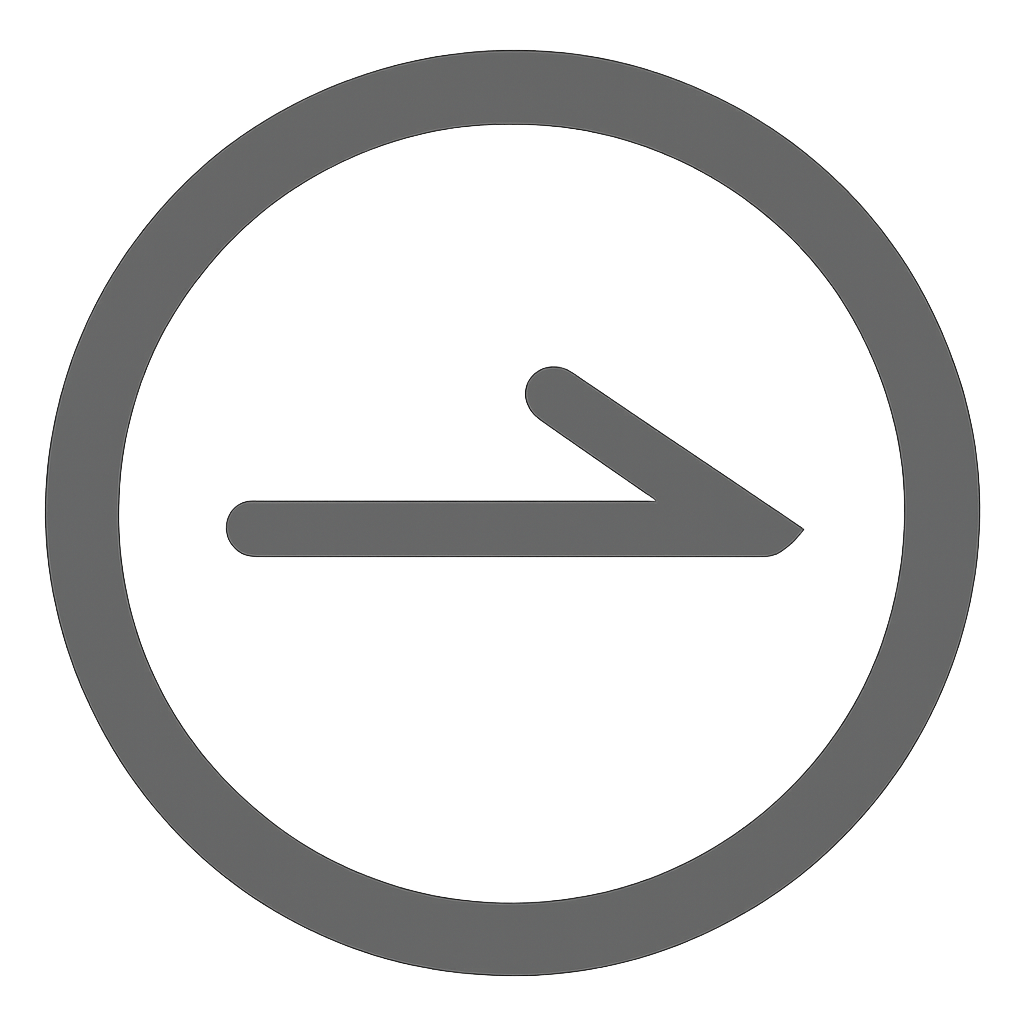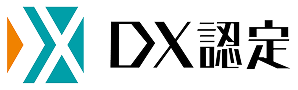「リーサス」とは何か?ユースケースや事業計画書への活用方法を解説
地域経済分析システム(RESAS:リーサス)は、経済産業省と内閣官房が共同で提供する、日本最大級のオープンデータプラットフォームです。2025年3月7日には、ユーザーの利便性と分析機能をさらに向上させた新システムがリリースされました。本稿では、リーサスの進化した機能や活用方法、特に事業計画書作成における具体的な活用事例について、中小企業診断士の視点からわかりやすく解説します。
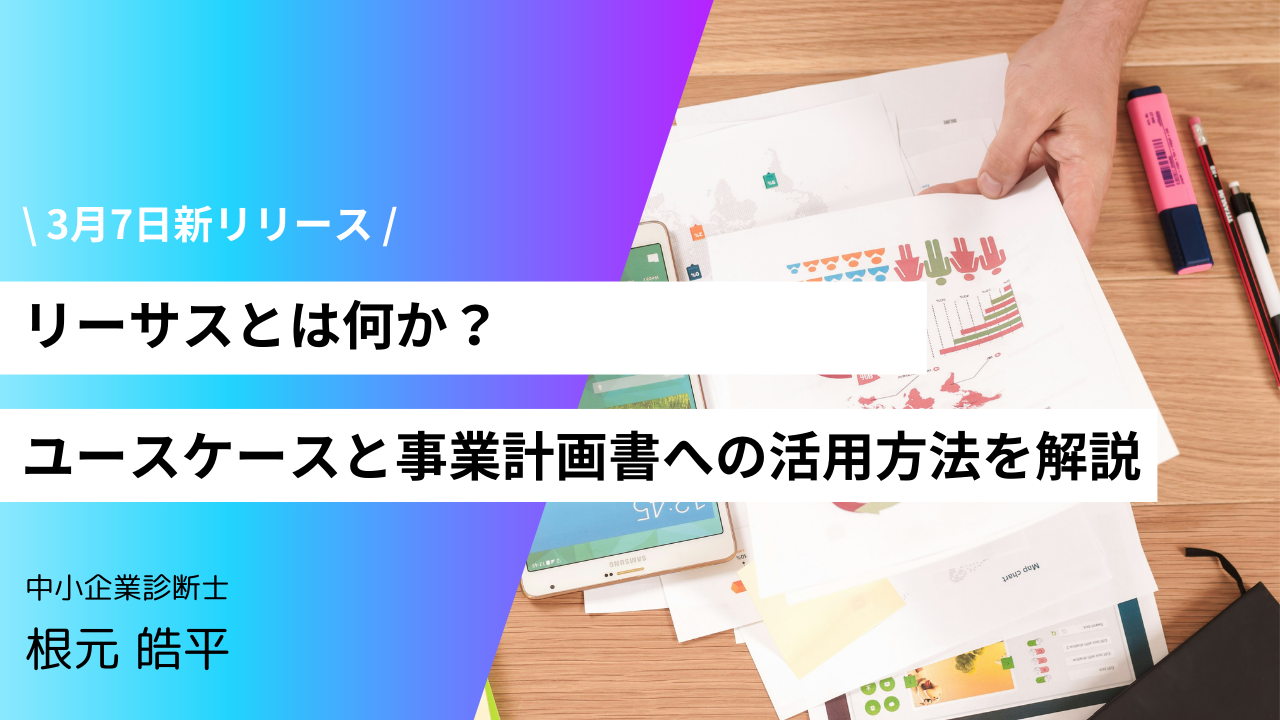
1. リーサスとは
リーサス(RESAS:Regional Economy Society Analyzing System)は、地域経済に関連する多様な統計データを一元的に集約し、視覚的に閲覧・分析できるように設計されたオープンデータツールです。
収録されている主なデータには、人口動態、産業構造、商業施設の売上、観光動向などがあり、これらはすべて無料で利用できます。地域の実態を正確に捉えることで、戦略立案や意思決定に根拠を与える手段として、自治体はもちろん、民間企業、研究者、学生など、幅広いユーザーに活用されています。
2. リーサス導入の目的
2.1 地方創生の推進
2014年に政府が掲げた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、人口減少や高齢化が進む地方の活性化が重要な政策課題とされました。地方自治体が自らの地域の特性や課題を正しく把握し、的確な施策を立案できるよう、データに基づく分析支援が求められていたのです。
2.2 エビデンスに基づく政策立案(EBPM)の実現
これまでの政策は、担当者の経験や主観に頼る場面が多く、政策の妥当性や効果を客観的に評価するのが困難でした。リーサスは、政策立案における客観的な根拠=エビデンスを提供するツールとして、EBPM(Evidence-Based Policy Making)の推進を支援するために整備されました。
2.3 官民データの利活用促進
リーサスでは、国や自治体の統計データに加えて、民間企業が保有するビッグデータ(購買履歴、SNS分析、GPS情報など)も統合し、より現場に近い実態を反映した地域分析が可能になっています。これにより、官民連携による高度な意思決定や地域課題の可視化が実現します。
3. リーサスの歴史
リーサス(RESAS)は、地域経済に関する多様なデータを一元化し、視覚的に「見える化」することで、地方創生を支援する目的で開発されました。その歴史は以下の通りです。
■ 2015年4月:RESAS 公開
経済産業省と内閣官房(地方創生推進室)が共同で開発し、自治体や事業者が地域課題の分析と政策立案に活用できるツールとして一般公開されました。
■ 主な特徴(初期)
– 官民のビッグデータを統合
– 地図・グラフによる直感的な可視化
– 地方自治体職員、企業、研究者、学生などが利用対象
■ 2015〜2020年:データ拡充と普及促進
観光、産業、人口、雇用など、カバーする分野を順次拡大。全国の自治体での活用が進み、各地でセミナーやワークショップも開催されました。
■ 2020年:教育向けe-RESAS提供開始
中高生が地域課題を学び、データをもとに探究学習を行う「e-RESAS」がスタート。教育現場での活用が広がりました。
■ 2023年:リニューアル方針発表
ユーザーの利便性と操作性向上を目的とした全面リニューアルの方針が発表されました。
■ 2025年3月:新RESASリリース
2025年3月7日、新システムが提供開始。以下の点が改良されました。
– 描画速度の高速化
– 類似メニューの統合による操作性向上
– スマートフォンへの完全対応
– 搭載データの精緻化
4. リーサスに含まれる主なデータカテゴリ
1. 人口・社会
年齢別人口構成
人口の増減(自然増・社会増)
転入・転出数(市区町村別)
世帯数の推移
外国人住民数
✅ 使い方例:地域の人口動態を確認し、マーケット規模や労働力の将来予測に活用
2. 産業
業種別の事業所数・従業者数・売上高
経済センサス・法人企業統計
特定業種(製造業・小売業など)の地域分布
特産品・地場産業のデータ
✅ 使い方例:地域の主要産業や成長産業を分析し、事業展開や連携先を検討
3. 観光
宿泊者数(日本人・外国人別)
外国人観光客の出身国別構成
観光地への訪問者数(GPSデータ等)
旅行消費額
✅ 使い方例:観光事業の需要分析や、外国人向けマーケティング戦略の策定に
4. 地域経済循環
地域内GDPとその構成
域内消費・生産・所得の流れ
「地域で稼ぐ力」の可視化
地域間の収支バランス
✅ 使い方例:地域経済の強みや課題を俯瞰し、産業振興の方向性を検討
5. 商業・消費
業種別販売額(商業統計)
消費支出の構成(家計調査ベース)
購買力(年収・可処分所得のデータ)
百貨店・スーパーなどの売上情報
✅ 使い方例:消費傾向や購買力を見極め、商品・サービスの展開方針を決定
6. 労働・雇用
年齢別・職種別の労働人口
有効求人倍率
雇用吸収率(地域での雇用力の指標)
離職・転職者の動向
✅ 使い方例:人材採用の難易度や人材不足リスクを分析、拠点戦略に活用
7. 企業活動
法人の設立・廃業数
ベンチャー企業の数
産学官連携データ(一部)
中小企業の分布や経営指標
✅ 使い方例:地域の起業活性度や協業の可能性を探る
8. 教育・人材
高校・大学の進学先や就職先
地域の学力・教育機会
地域別の進学率・就職率
✅ 使い方例:人材流出入の傾向や若者の定着度を分析し、人材戦略に反映
9. 移動・交通
通勤・通学の流動データ
鉄道・道路交通量(民間GPSデータ等)
自動車保有台数
✅ 使い方例:人の流れを分析し、店舗立地や交通インフラ整備の参考に
10. 災害リスク・社会インフラ(限定)
一部の地域でインフラ整備状況や災害関連データも閲覧可能
✅ 使い方例:事業継続計画(BCP)やリスク分析の基礎データに
■ 民間データの統合例(V-RESASやe-RESAS等)
リーサスでは、政府統計だけでなく、以下のような民間企業のビッグデータも一部取り入れています。
GPS位置情報(移動傾向分析)
レビュー・SNS投稿データ(観光や飲食業の評価)
POSデータ・カード決済情報(消費傾向の把握)
5. 民間企業におけるリーサス活用のユースケース
1. 出店・新規事業の立地選定活用例:
小売業・飲食業・サービス業などが、新規店舗や支店を出す際に、地域の人口動態や商圏分析を行う。
例えば「20代~30代の人口が増加している地域」や「競合が少ないエリア」を特定して出店戦略を立てる。
利用するRESAS機能:
地域別人口構成・世帯数
年齢別転入出データ
業種別事業所数や売上
2. 地域密着型マーケティングの戦略立案
活用例:
地域ごとの消費傾向や観光動向を分析し、ニーズに合わせた商品開発やプロモーションを実施。
例:観光需要が高いエリアに「お土産商品」を展開、外国人観光客の多い地域向けに多言語対応の販促物を用意。
利用するRESAS機能:
観光マップ(宿泊者数、外国人訪問者数)
商業統計(販売額・業種別の売上構成)
消費支出データ(品目別支出額)
3. 競合調査・市場ポジショニング
活用例:
地域ごとの競合店舗数、業種の伸び縮みを確認して、自社のポジションや差別化戦略を検討。
例:美容業界で出店を考えている会社が、特定地域の美容室の数や売上推移を確認し、ブルーオーシャンを狙う。
利用するRESAS機能:
業種別の事業所数と増減推移
地域内経済循環マップ(どの産業が域外から稼いでいるか)
雇用・労働構造データ(職業別人口など)
4. 地方進出・移住支援サービスの企画
活用例:
不動産・住宅関連企業が、地方移住ニーズの高い地域を特定し、住宅提案や移住者向けサービスを展開。
例:テレワーク移住希望者向けに空き家活用サービスを立ち上げる。
利用するRESAS機能:
移住者の流入出トレンド(市町村別)
年齢別人口推移(地域の活力を確認)
空き家率・住宅統計(※RESAS自体では一部の住宅データのみ)
5. 人材採用・拠点戦略の最適化
活用例:
新拠点を設置する際に、その地域に必要なスキル人材がどの程度存在するか、また雇用状況を分析。
例:製造業が人手不足を避けるため、若年層労働人口の多いエリアを選ぶ。
利用するRESAS機能:
職業別就業者数
年齢構成別労働力人口
雇用吸収率や転出入データ
6. 事業計画書や補助金申請書の裏付け資料として
活用例:
中小企業がものづくり補助金やIT導入補助金などを申請する際、マーケット分析の根拠としてリーサスのデータを引用。
例:地域の需要増加を示す人口推移データを事業計画に活用。
利用するRESAS機能:
地域別人口・産業データ
商業統計・産業構造データ
地域経済循環マップ
以下では事業計画書の裏付け資料としてリーサスをどのように活用出来るのかを解説していきます。
リーサス 活用解説(事業計画書編)
6. 事業計画書とは
事業計画書は、企業や団体が事業の方向性や目標、実行内容、財務見通しをまとめた文書であり、経営戦略の基本となる資料です。新規事業の立ち上げや資金調達時にはもちろん、補助金申請においても必須とされています。
中小企業庁が公表する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(通称:ものづくり補助金)では、3〜5年を見通した具体的な事業計画の策定と実行が求められています。
主な補助金制度の例:
– ものづくり補助金
– IT導入補助金
– 小規模事業者持続化補助金
いずれの制度においても、事業計画書は「事業の実現可能性」と「成長性」を説明する重要な書類となります。
7. 事業計画書の標準的な構成
以下は、ものづくり補助金をはじめとする補助金申請における、一般的な事業計画書の構成です。
■ 7.1 補助事業の具体的取組内容
– 自社の概要(沿革、事業内容、体制など)
– 現状の課題とその背景
– 解決策としての取組内容
– 実施スケジュール
– 実行体制と関係者の役割
– 想定される成果と効果
■ 7.2 将来の展望
– 対象とする市場・顧客の特徴
– 中長期的な収益目標や成長戦略
– 地域経済への貢献、雇用創出等の社会的波及効果
■ 7.3 会社全体の事業計画
– 売上・利益計画(5年分)
– 設備投資や資金調達の計画
– 収益見込みとその根拠(積算)
これらの項目を網羅することで、審査側にとっても信頼性の高い計画書になります。
8. 事業計画書にリーサスをどう使える?
リーサスを活用することで、事業計画書の内容をデータに基づいて補強することが可能です。以下のような項目に特に有効です。
■ 8.1 市場分析
人口構成や産業データから、ターゲット市場の規模や成長性を把握できます。出店予定エリアの年齢別人口や所得分布を見ることで、適切な市場選定が可能になります。
■ 8.2 顧客ニーズの分析
観光動態や消費支出データをもとに、地域の消費者が何に関心を持っているかを把握できます。商品の開発や販促戦略の根拠として活用できます。
■ 8.3 競合分析
同業他社の立地や業種別の事業所数、売上の推移を確認し、競争状況を分析できます。自社の強み・弱みを整理し、差別化の方向性を導き出せます。
■ 8.4 売上予測
地域の消費支出や業種別売上データを基に、現実的な売上予測を立てることができます。収益計画の信頼性向上に貢献します。
■ 8.5 ターゲット戦略
世帯構成や年齢構成、購買力データから、誰に向けた商品・サービスを提供すべきかを明確にできます。
■ 8.6 人材確保・雇用戦略
職種別の労働力人口や有効求人倍率のデータにより、採用戦略を立てる上での根拠を得ることができます。
■ 8.7 事業拡大の判断
経済成長率や人口推移などのマクロな指標から、事業の将来性を数値的に把握できます。
これらの項目にリーサスのデータを活用することで、事業計画書はより説得力と実現性を持ったものになります。
9. まとめ
リーサスは、補助金申請や新規事業立案に必要な事業計画書の作成を強力にサポートするツールです。
特に、客観的なデータに基づいた「市場分析」「競合調査」「売上予測」などの要素を加えることで、計画書の説得力を高めることができます。
中小企業や個人事業主にとって、リーサスは無料で使える“地域戦略のための情報インフラ”です。
事業の可能性をデータで証明し、実現へと導くために、ぜひ活用してみてください。